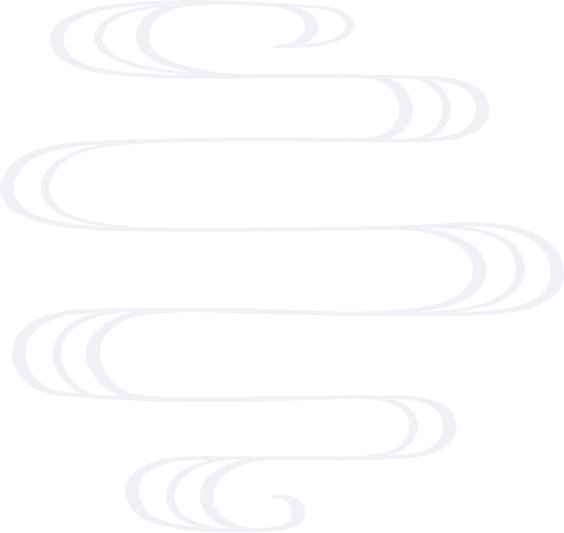皆様からよくご質問をいただく焼香のやり方についてご紹介いたします。
焼香の作法
焼香の作法にはいくつかのステップがあります。これらを正しく行うことで、心を落ち着け、故人への敬意を表すことができます。焼香を行う際は、一つ一つの動作に意味が込められていることを意識し、丁寧に行うことが大切です。
焼香の準備
まず、焼香を始める前に場所を整えます。香炉を用意し、その隣に香と火を置きます。香炉は通常、仏壇の前に置かれ、静かな環境を整えます。周囲の騒音をできるだけ避け、落ち着いた雰囲気を作ることが重要です。心を込めた祈りを捧げるための準備は、精神的な集中を高めるための第一歩です。
香炉の準備が整ったら、香の種類や量を選びます。香の選択は個人の信仰や意図により異なりますが、一般的には穏やかな香りが好まれます。香を扱う際は、慎重に取り扱い、香が持つ意味を大切にしましょう。香の準備を終えたら、心を落ち着けて焼香の儀式に臨みます。
焼香の基本的な作法
焼香には、立って行う「立礼焼香」、座って行う「座礼焼香」、席に座ったまま香炉を回して行う「回し焼香」があります。いずれの場合も、基本的な流れは以下の通りです。
- 焼香台(または香炉)の手前で、遺族と僧侶に一礼する。
- 焼香台の前に進み、遺影に向かって一礼する。
- 数珠を左手にかけ、右手の親指・人差し指・中指の3本で抹香(粉状のお香)をつまむ。
- 宗派によって定められた回数、抹香を香炉に落とす。
- この際、額の高さまでつまんだ抹香を掲げる(押しいただく)宗派と、そのまま落とす宗派がある。
- 合掌して故人の冥福を祈る。
- 遺族に一礼して席に戻る。
焼香の回数
- 天台宗
- 回数: 1回または3回。特に決まりはないが、僧侶は3回。
- 作法: つまんだ抹香を額に押しいただき、香炉に落とす。
- 真言宗
- 回数: 3回
- 作法: つまんだ抹香を額に押しいただき、香炉に落とす。
- 浄土宗
- 回数: 1回〜3回
- 作法: つまんだ抹香を額に押しいただき、香炉に落とす。
- 浄土真宗
- 浄土真宗本願寺派(お西)
- 回数: 1回
- 作法: 押しいただかず、そのまま香炉に落とす。
- 真宗大谷派(お東)
- 回数: 2回
- 作法: 押しいただかず、そのまま香炉に落とす。
- ※線香を用いる場合は、香炉のサイズに合わせて折ってから火をつけ、横にして寝かせる。
- 浄土真宗本願寺派(お西)
- 臨済宗
- 回数: 1回
- 作法: 押しいただかずに、そのまま香炉に落とすのが一般的。
- 曹洞宗
- 回数: 2回
- 作法: 1回目は「主香(しゅこう)」といい、額に押しいただく。2回目は「従香(じゅこう)」といい、押しいただかずにそのまま落とす。
- 日蓮宗
- 回数: 1回または3回
- 作法: つまんだ抹香を額に押しいただき、香炉に落とす。
宗派が分からない場合
宗派が分からない場合は、焼香の回数を1回または3回にするのが無難とされています。 また、参列者が多い場合は、司会者から「1回焼香でお願いいたします」と案内されることもありますので、その指示に従いましょう。

焼香の作法について、まとめ
焼香は、香を焚くことで仏や故人に敬意を表し、自らの心を清めるという意味があります。香の煙は、仏や故人への供物として捧げられ、同時に自分自身の心の浄化を図る行為でもあります。この行為は、心を静め、祈りの場にふさわしい空気を作り出します。
また、内面的な静けさを促進するための手段でもあります。香の芳香は、感覚を研ぎ澄まし、心の安らぎをもたらします。香を焚くことによって、私たちは一瞬の静寂を享受し、心の中の雑念を取り払うことができます。さらに、香の煙は仏教の教えにおける無常観を象徴し、すべての存在が移り変わっていくことを思い起こさせます。